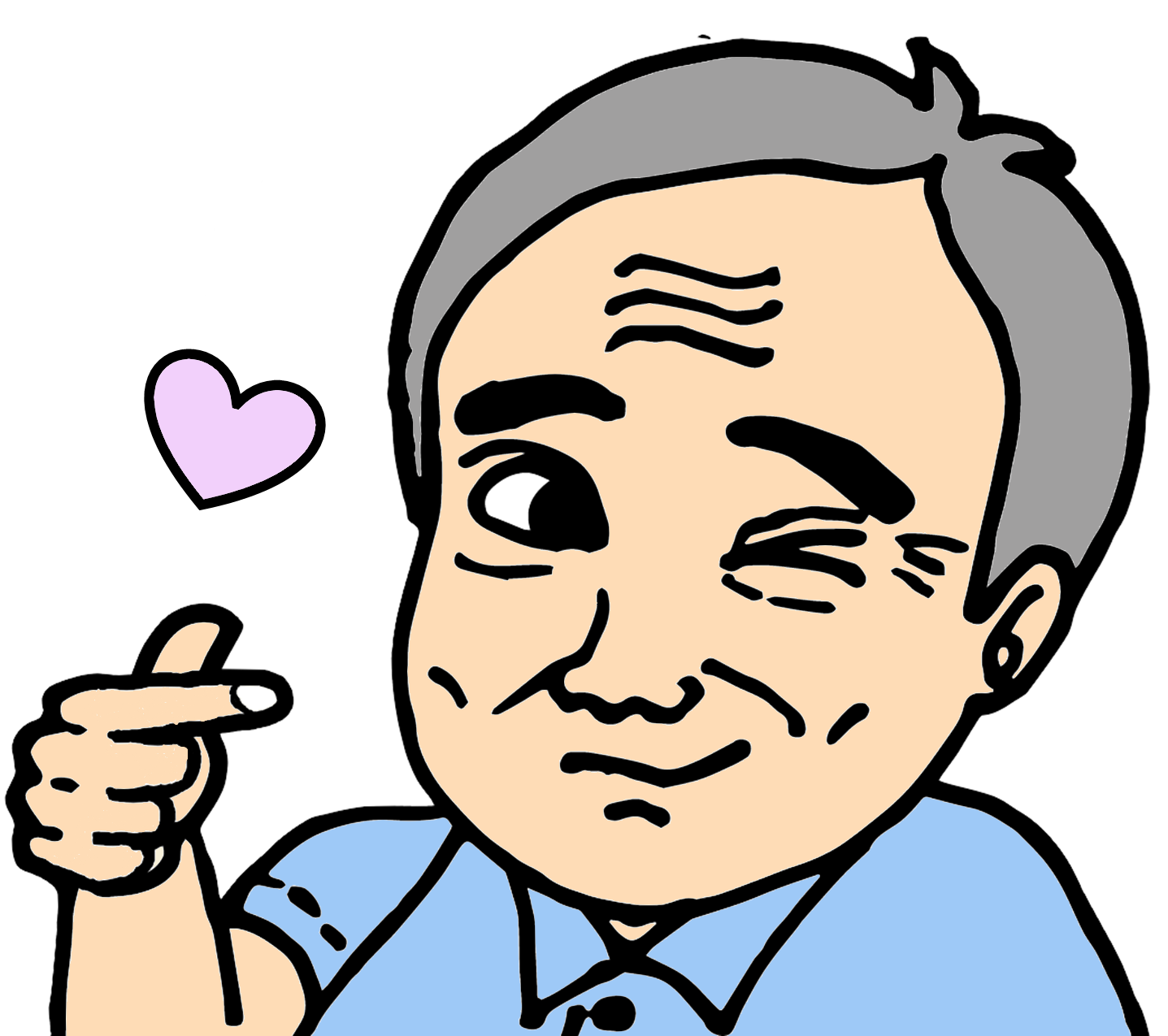今は昔、竹取の翁といふものありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。
中学一年の国語で「竹取物語」の授業をしていて、上記の冒頭部の内容にふれていた際、ある生徒が質問した。
「最初に、『竹取の翁』と紹介してるのに、あとで『名前をさぬきのみやつこ』と、また紹介するのはなぜ?」と。
ある意味とても鋭い疑問かと思って、考えてみた。即興で答えねばならないので、時間は取れなかったが、他に私自身の中でくすぶっていた疑問とつながるかもしれないと思い、「係り結び」とからめて講釈してみた。
「一文目と三文目で違うとこがあるとすれば、皆はどこだと思う?」と問い返す。
生徒たちからのいくつかの返答の末、ようやく「一文目では使われていない『なむ』が三文目では使われている」とあがった。
「係り結びであるため文末が『けり』ではなく『ける』になっていることは、前に説明したとおり古典の法則なのだが、どういうときに係り結びを引き起こす「なむ」を使うのか考えてみなかったよね?」と投げかけ、時間をかせぎながら私自身も思考をめぐらす。
「訳したところで、『なむ』の部分を決まった訳し方があるわけでもなく、面に表れてこないよねぇ⁉」「どんな時に『なむ』をつけるんだろう?」さらに疑問を投げかける。
すると、ほどなくある生徒から「強調したい時!」とでる。
「しめた!」とわたしはほくそ笑む。「正解!物事を強調したい時に『なむ』が使われるんだね。現代の言葉で言うと『こそ』なんかがそれにあたるよね~^^。」「と、いうことは‥‥、一文目と三文目だったら、書いた人(作者)はどっちをより読み手に印象付けたかったんだい?」
「三行目!」「三行目~!」
「そう、つまり『なまえを、さぬきのみやつこという』ということを読者には強く印象付けたかったんだろうね。」「でもさ、なんでことさらここで『なまえ』を強調するんだろうねぇ?『名前は山田太郎と言いました。』って強調されたって、『だから、何?』って感じじゃない?何をいまさらでしょ⁉」
生徒の多くはうなづいている。「きっとね、強調したいのは『さぬきのみやつこ』であるということなんだろうね。」「『さぬき』は地方の名なのかなぁ。『みやつこ』は漢字で書くと『造』らしいから、そこから想像してみよう。」
こうして竹取の翁の人物像(キャラ)が浮かび上がってくる。最終的には「モノづくりの名手」であることを認識する。二文目とあいまって、このあたりではちょっと名の知れた(有名な)竹細工の作り手であることをである。続けてたたみかける。「この翁は単に竹を取っているどこにでもいるじいさんではなく、その自分のとった竹で物を作る腕のたつ老職人であることを強調したかっただろうね。『名をば(名前を)』って教科書でも訳してはいるが、それは実名ではなく称号みたいなものと考えればいいでしょう。」と結ぶ。「野球界のミスター」といえば長嶋茂雄さんのごとく。
この後、かぐや姫は翁の家に連れて帰られて、媼に籠の中で育てられる運びとなるが、この籠も言わずもがな翁が竹で自ら作ったものだろうとたやすく想像できる。
翁について、冒頭で描かれた人物像については、先ほど言った私自身の疑問点とからめて続ける。「先生は、二文目の『野山にまじりて』のところが、昔からしっくりこなかったんだよ。教科書では『野や山に分け入って』って訳しているけど、君ら『分け入って』って訳されても逆に難しく思えてわかりにくくない? 『分け入る』というのは、『草や木をかき分けて、奥に入る』って意味なのだが、こうやってさらに解説しなきゃいけない感じになっているのが不自然でね。」「先生は、ある仮説を立ててみました。これは、さっき君らから出てきた疑問『なんで二回も翁の紹介するの?』を解くことによって、確証が高まったことなんだ。教科書をはじめ古語辞典やネットで調べても『まじりて』とは用例付きで『まじる‥‥分け入って(野山にまじりて【竹取物語】)って口をそろえたように書いてあるのよ。まるで竹取物語の冒頭部に出てくる『まじりて』は、『分け入って』と訳すのだといわんばかりに‥。で、仮説というのは、最初のころに『竹取物語』を訳した人が『分け入って』って訳したから、その後の人も辞書も追随して『分け入って』になっちゃたのかなぁって思うんだ。そう訳すのが決して間違いではないし、翁はきっと草をかき分けて竹の山の中に入っていっただろうけど‥‥。そこは、普通に訳した方がいいんじゃないかって思うんだ。現代でも使う『まじる』(溶け込む、一緒になる、一体化する)という意味で考えればいいじゃん。そういった意味での使い方は奈良時代ころからされてきたわけだし、ことさらなんで竹取物語では『分け入る』にしなきゃならんのか、腑に落ちなかったんだ。だから先生は。こう考えています。『野や山と一体化して(とけこんで)、つまり自然と融合して竹を取っている爺さん(自然とともに共調しながら毎日の生活を送っている翁)』って感じ。そうすれば、竹取の翁の人柄というか人物像がよりくっきりとしてくるではないですか。『毎日を自然の声を聴きながら竹の林に入って生活している翁だからこそ、根元が光る竹を発見できたのでしょうか』といったつながりのあるイメージへと膨らますことができるのじゃないかって思ったのよ。翁という人物、決して派手ではないが、たしかな腕を持ち、自然を愛し、静かに、生真面目に、そして優しい心をもって生活しているキャラクター。こう考えた方がより豊かに物語を味わえるように思えるんだ。」
物語には伏線が張られてあり、あとでなるほどここにこうつながるのかと思うことがある。教科書では「言葉遊び」ということで紹介されている。例えば、かぐや姫から与えられた難題のうち中納言石上麻呂足(いそのかみのまろたり)の場合は、目指す燕の子安貝をつかんだと思ったところで崖から落ちてしまう。手にしていたのは貝ではなく、鳥の糞であったとこから、苦労した末無駄であったことを「貝なし」→「甲斐なし」と言うようになったとある。言葉遊びと言葉の成り立ち(いわれ・由来)をこめて書いているようだ。かぐや姫から贈られた不死の薬を時の帝は天に最も近い山で燃やすよう命じる。「不死の薬を焼かせた山→ふしの山」のイメージを感じさせつつ、命を受けた使者はたくさんの兵士を引き連れて山を登る「士に富む山→ふしのやま」とし、この後者が富士の山という名称のついた由来であるとくくっている。「なよ竹のかぐや姫」と名付けたのは翁に呼ばれた御室戸斎部(みむろといんべ)の秋田であるが、当時の読み手となる人々は「かぐはし姫(におい立つほど美しい姫)」とイメージしていたのではないかと思う。そこに耀(かがよ)う(光輝くほどに美しい)姫と掛け合わせているようにみえる。「なよ竹」については、出てきたのが竹だから竹はわかる。「なよ」は現代の「弱々しい」という意味よりは「柔軟さ、清純さ、若々しさ」をイメージさせる。言葉を巧みに用いて人物像や心情・情景・状況を誘引する仕組みになっている。突っ込みどころも満載である。わずか三寸で発見されたかぐや姫、三か月のちには一人前の娘となってしまう。この勢いで成長してったならば、くらもちの皇子がにせの玉の枝をつくらせてかぐや姫の前に訪れた三年後には百八十歳、18Mの巨女になっちゃう。月に帰る6年後にはその倍になっちゃうぜ。と、読者を楽しませておいて、いやいや、「竹」だけに初めは勢い良く伸びるが、その竹だって限りなく伸び続けるわけではないから、そういう意味では整合性がとれているのかなぁと思わせてもくれる。伏線とも思える数々の仕掛けを施し、読者と対話するように、なぞかけのように楽しませる工夫のなされた竹取物語。これが現存する最古の物語。最初の物語にしてはとてつもなくよくできた作品といえるだろう。
2019年の現在、「ふじのやま」を我々は漢字で「富士山」と書いている。竹取物語が書かれたであろう1000年以上前には、「不二」「不尽」などさまざまな表記があったであろう中、竹取物語では「富士」であると名の由来を述べている。この竹取物語が採用した「富士」を1000年後の我々も当たり前のように使っている。竹取物語が「富士」って漢字の名付け親なのかなと思えてしまう。1000年以上も前のその当時、不死の薬の壺を焼かせたとされる煙が立ち上っていると記している。あぁ、そのころ富士山は火山活動していたのだなという別の事象をも教えてくれるのである。
御文、不死の薬の壺並べて、火をつけて燃やすべきよし仰せたまふ。
そのよしうけたまはりて、士どもあまた具して山へ登りけるよりなむ、その山を「ふじの山」とは名づけける。
その煙、いまだ雲の中へ立ち上るとぞ、言ひ伝へたる。
この最後の場面の「なむ」-「ける」の係り結び。
それとは次元の違う「ぞ」―「たる」の係り結びでしめくくる。「たる」に込められた存続の意味合い。「昔から-今も-そしてこれからも」
千年の時を超えて、未来の人も読みあじわうであろうと語りかけるこの臨場感が、私になんともいえぬあじわい深い余韻として漂っているのである。
END