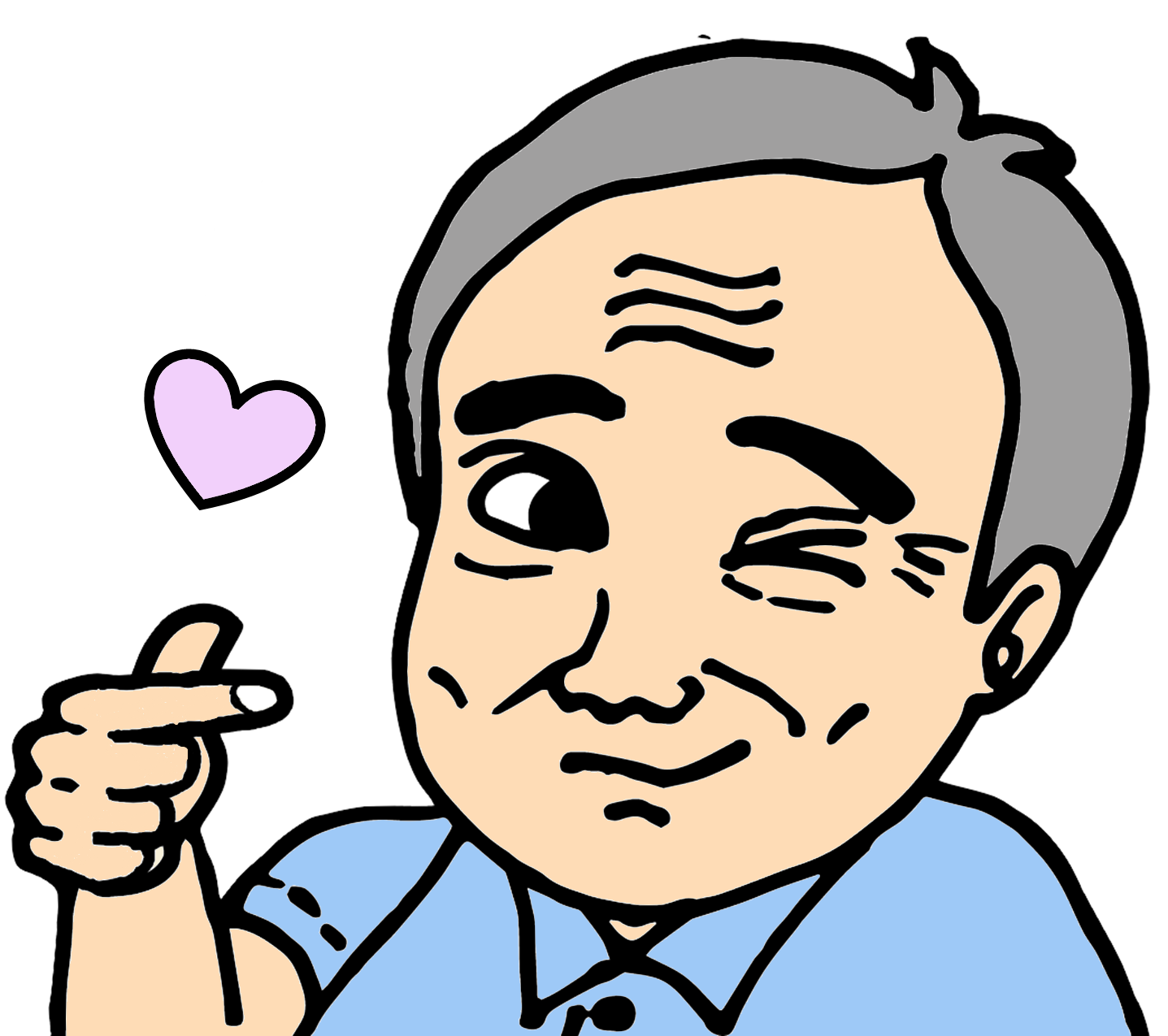二人の若い紳士が(二人のチャラい若者が)イギリスの兵隊の形をして(それっぽい恰好をして)鹿狩りとシャレこんで入った山奥。いつの間にか案内人も消え失せ、連れてきた二疋の白い犬も泡を吐いて死んでしまう。死んだ犬について、「ぼくは○○円の損害だ」と口々に言い合う。二人は、釣果の得られぬ釣り人のごとく「昨日の宿屋で、山鳥を拾円も買って帰ればいい。」と言って帰ろうとする。しかし、戻る道がわからなくなり困窮する。その後の展開はみなさんもなんとなくわかるでしょう。ここに登場した二人の若者は現代にもよくある普通の若者と同じです。ちょっと格好つけてシャレこんで鹿狩りでもっていうごくごく軽いノリで楽しもうとしている様子です。それが、悪いことだとは言えませんよね。歳をとった人だって同じように思ったりした経験はあるはずです。どこにでもいる普通のこれといって悪いことはしていないとされる人間。彼らに起きた災難?最後に蘇ったのか白い犬と簔帽子をかぶった専門の猟師に助けられる結末とはなりますが、「そして猟師のもってきた団子をたべ、途中で十円だけ山鳥を買って東京に帰りました。」山鳥買って帰るんかい!と突っ込めました?「しかし、さっき一ぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯にはいっても、もうもとのとおりになおりませんでした。」でおしまいとなります。痛い目にあったはずの若者は、結局のど元過ぎれば熱さ忘れて、また同じことを繰り返すのでしょう。それにくぎを刺すために顔がくしゃくしゃのままとしたのかもしれません。宮沢賢治は根本的に変わらぬ人の根に悲しみを憶えたのでしょう。鹿や山鳥を自分の趣向として楽しむためにだけ撃ち、自慢するためにだけ持ち帰る。連れてきた犬が死んでも、その死を悼むどころかいくら損したかと考える。蘇った犬に助けられてもありがたみも持たず。山鳥を買って何事もなかったかのように格好つけて帰っていく。彼らには経験から学ぶ資質がなかったようです。
世の中ってそんなもんだと思いませんか?宮沢賢治が生きた時代も同じようだったのでしょう。自分のことしか考えず、自然の摂理には逆らい、わかった風をよそおいはするが決して理解しようとはしない人の心根を彼はあばいていったのだと思います。「オツベルと象」でも人と人の理解していそうで理解してない点を描いていると私は見ています。
世の中に疑問・矛盾を感じた時、人はまた同じ過ちを繰り返すのではと勘ぐってしまう次第です。
上記は、「白髪レガシーVol.31 『迷路を彷徨う社会』 2019.11.17」 に載せたものです。