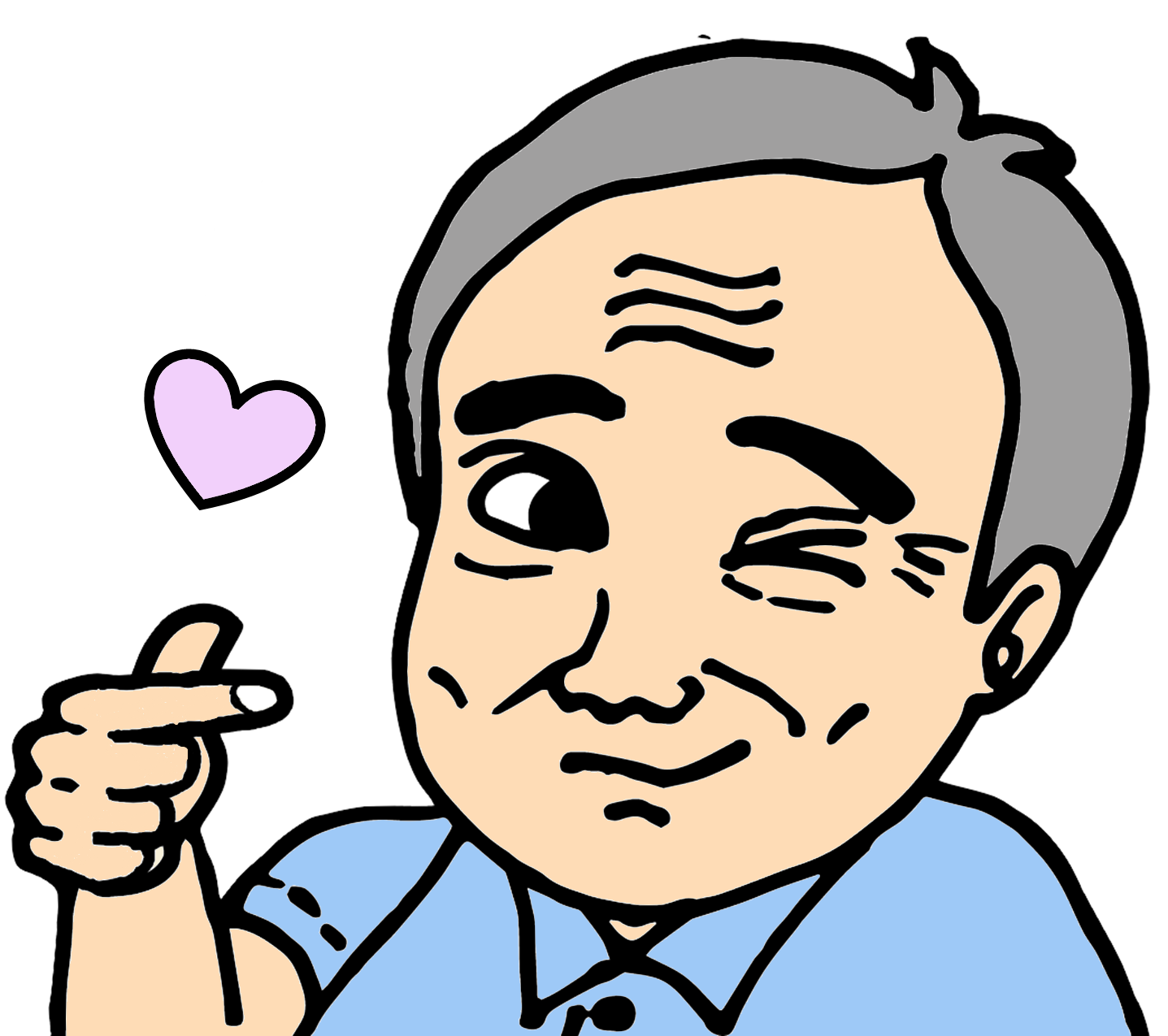先日作った「おくのほそ道」の学習プリントの裏に記した「芭蕉の想い」に「『古人』宗祇について」を追記したものです。
芭蕉の想い
「おくのほそ道」は中学国語の集大成である。
紀行文ではあるが、そのような文学ジャンルには収まりきらないものと言える。
「つながり」という点に着目する。「芭蕉」ならば、彼に影響を与えた人とは、古人(李白・杜甫・西行・宗祇)である。しかし、この四人だけではないのであろう。西行で言うなれば、西行が何を思い旅をしていたのかという本質に迫りたかった気がしてならない。どんな状況下で何を案じ、何をしようとしていたのか、古人の時代の中における様態と同化したかったのではなかろうか。同化できれば思いの底が垣間見えると信じたのではなかろうか。西行は二度陸奥への旅を志した。一回目の理由は定かにされてはいないが、西行が師と仰ぐ能因法師の足跡をもって境地を知りたかったのではないか。このように「古人」がさらなる「古人」の境地を知ろうとする繋がりが見てとれる。西行二回目の陸奥への旅は名目上君らも行く予定であった奈良東大寺焼失に伴う勧進であったとされる。途中鎌倉で源頼朝と面会したのは、旅の目的を伝え、平泉巡行の許可を得るためとされる。西行と奥州藤原氏は祖先に鎌足公を持つもの、いわゆる親戚である。それを知っているうえで頼朝は許可したしたのであろう。
鎌倉(中央)が奥州(藤原氏)に睨みをきかせる構図。そのはざまで隠密のごとく平泉へ向かう元武士西行。
芭蕉がおくのほそ道の旅に出た一六八九年に照らすと、「東照宮元禄の大修理の命が伊達藩に命じられた」頃と考えられ、江戸(中央)が伊達藩(仙台藩)に睨みをきかせた構図となり、西行の奥州行の頃と符合する。
おそらく芭蕉は敬慕(尊敬)する師である西行の心境に少しでも近づかんとしたのであろう。「おくのほそ道」の旅は、西行巡礼の旅であったと言える。
では、なぜ芭蕉は平泉の後、北陸(日本海)を通るルートをとったのか。芭蕉は、義経を案じていたであろう藤原秀衡を訪ねた西行の動向とも重なり、源義経が平泉へ逃げ入ったルートを模索する意味で(源義経が平泉に入ったルートは明らかにされていない) 、その候補の一つ、義経記や歌舞伎の演目「勧進帳」にある北陸路を逆走するルートを採ったのではなかろうか。芭蕉自身も義経や弁慶に対する想いを強く持っていたのだろう。
「繋ぐもの」は「勧進」という名目。山伏に化けて東大寺勧進の旅であるとして難関突破を図った「勧進帳」。東大寺への寄進(勧進)として、黄金の国ジパングと世界に轟かせることとなる平泉に赴く西行。御恩と奉公のはざまで苦しむ伊達藩を気づかっているかの芭蕉。
白河の関は、藤原秀衡が自分たちの勢力の及ぶ目安であり、なんとか義経一行がそこを越え逃げ延びてさえくれればと願った地点でもあろう。
「時の旅人」と言えるものは、李白、西行。「時間」という概念を詩に盛り込み、古人の想いに寄り添った。芭蕉もしかりである。
「おくのほそ道」冒頭は、時の中に留まる「自分の家=芭蕉庵」を旅立たせる門出の段であったと言える。庵の柱に掛けた面八句には、「草の戸も‥‥」の発句一句のみが記されており(俳諧連歌の師、宗祇をたてたものと思われる)、その続きは、庵が新たな住人とともに新たな人生を紡いでいってほしい(連句として書き綴っていってほしい)と願った庵の門出の段なのだ。
「おくのほそ道」「平泉」のところで、芭蕉が思い浮かべる「国破れて‥‥」という杜甫の詩「春望」の一節。この無常観のルーツとあいまって、芭蕉の芸術(蕉風)的境地と共鳴したのであろう。
事実と虚偽は区別しなくてはならぬだろうが、わからないところは、想像を駆使し、想像を確かめるべく、感じ取るべく動いた古人がいたとしてもおかしくはないだろう。その一人が芭蕉なのである。 2021.9.1
「古人」宗祇について
「古人」と呼ばれる四人の芭蕉の敬慕する詩人歌人の中で、中学の学習の中で現れてこない「宗祇」が、どんな点から芭蕉が尊敬する人物と言えるのか、生徒たちの中には疑問に思う者もいるだろう。
「宗祇」については、和歌山県有田郡有田川町のホームページにこう紹介されている。 (有田川町のホームページ https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kanaya/7/2/1/578.html より抜粋
「心の連歌師」宗祇法師
定輪寺蔵
宗祇は西行、松尾芭蕉と並んで 放浪三代詩人と呼ばれるとともに、連歌を大成し、幅広く世に広めた連歌界の巨匠です。
宗祇法師は応永28年(1421)、紀伊国藤波荘(有田川町下津野)で生まれたと言われています。幼少期については明らかではありませんが、やがて京都に上り、本格的に連歌に取り組むようになりました。 そして、代表作である「三無瀬三吟百韻」(みなせさんぎんひゃくいん)をはじめ、文化価値の高い作品を次々と発表しました。
当時の連歌が単にことば遊びのおもしろ味を競い、賭博を伴ったものであったのに対し、宗祇は格調高い文学性と芸術性の高いものへと変化させていきました。
やがて彼の名は全国に広がり、時の将軍足利義尚から連歌師としては最高の役職である「連歌会所奉行」を、朝廷(後土御門天皇)からは「花の下」(はなのもと)という最高の称号を与えられ、連歌師最高の位にまで達しました。漂泊の詩人とも呼ばれた宗祇は、諸国をめぐって連歌の普及に尽力しましたが、旅の途中に箱根湯本の早雲寺で82年にわたる生涯を終えました。その亡骸は弟子たちによって宗祇の愛した富士山に近い裾野の地の定輪寺に葬られました。
上記の下線の部分が、芭蕉の想いと交錯し、呼応するところだと思います。
宗祇が生きた15世紀(1400年代 室町時代)は芭蕉が生きた17世紀(1600年代 江戸時代元禄)から見ると、200年以上前の先生となります。格調高く芸術性の高い連歌を確立した宗祇。芭蕉が生きた時代では、俳諧というものが、また滑稽味を重んじる低俗なものが当たり前となっていたのでしょう。芭蕉は宗祇先生よろしく、俳諧を整合性たるまとまりもあり情緒もあるものへと返すべく尽力したのだと思います。これはのちの芭蕉の理念蕉風へとつながるものです。正統な俳諧理念の在り方を模索したところが、芭蕉が宗祇を敬慕した理由と言えるでしょう。
そんな宗祇師匠に敬意を表し、俳諧連歌(連句)百韻の型に倣い、「面八句」を柱に掛けたのです。しかし、「面八句」と言いながら、実際に芭蕉が記したのは、「発句」(草の戸も‥‥)のみだったと考えられます。「『面八句』が残っていない」とか「どれだけの人が集まった(俳諧の会だと思っているのでしょうか)記録がない」ということでうやむやされてきたのかもしれませんが、「発句」一句のみが書かれていたと断言します。多くの人の手を経て紡ぐ俳諧連歌。その(発句の)続きは新たな住人と庵とで、共に紡いでいってほしいという庵の新たな旅立ちを願ったことと考えれば結べるでしょう。このことから、「おくのほそ道」冒頭の部分は、「庵の旅立ち(門出)」の段だと思えるのです。
我が国の美意識を考えた時、「もののあはれ」がまずあげられるかと思います。「しみじみとした趣がある」などと訳されるものです。
平安時代後期なると仏教の「諸行無常」が「末法思想」と世の中の荒廃ぶりと交錯していったのでしょう。一般的にいうは「無常観」です。平家物語の「扇の的」に見てとれる「五十ばかりなる男」を射貫いた時の「余興の余韻が興覚めとなる空気の変化」という”無常”。また「情けなし(こころなし)」と源氏方の武士の反応にも見られた”無情”。
双方の「ムジョウ」が絡み合った美の価値観を生み出していく。「万物は移り変わってしまうはかなさをともなう非情さ」といった具合とでもいえばいいでしょうか。寂しくもはかない絶望的な「無常」は鎌倉時代になると、より「殺風景」な情緒と結び付きます。藤原定家はおそらく、新たな試みとして「空想の絵画」を絵画ではなく歌に興したのでしょう。まるで、「歌の枯山水」。理解してくれない者も多かったと思います。この究極の美を。
能(猿楽)・歌舞伎 といった多少なやましげであり滑稽でもあるものへ変化しつつ、俳諧連歌も横道にそれて別物にならんとしたころあらわれたのが芭蕉なのでしょう。これまで培われてきた美意識を統括したかに見えます。「もののあはれ」「無常」「空想」「変化」。しかも、単独・単発ではなく一連として最終的に何とも言えぬ良さを醸し出すことを目指しているふうに見えます。無意味なまでに派手にお茶らけていく美の価値観、無機質なまでにつき詰められた究極の美の価値観。美意識の格差のはざ間で辿り着いたのが、無機的な中にかおる有機的な前向きの心情だったのでしょう。ある面、「あはれ(しみじみとした趣のある)」に似ていますが、無常観の影響もあり、よりかすれた中に見とれる情緒なのでしょう。これが芭蕉の提唱する「さび」というものかもしれません。
夏草や兵どもが夢の跡
草の戸も住み替はる代ぞ雛の家
【かすれた渋めの景】実・現 【浮立つ前向きの景】寓・偶(想像)
「夏草」=雑草 ⇔ 「夢」=きらめきを夢見た秀衡や義経とその従
「草の戸」=川のほとりのあばら家 ⇔ 「雛の家」=きらびやかに生まれ変わった家
無常観の下地にあってほのかににおいたつ美の世界を夢見たのでしょう。
2021.9.10 追記