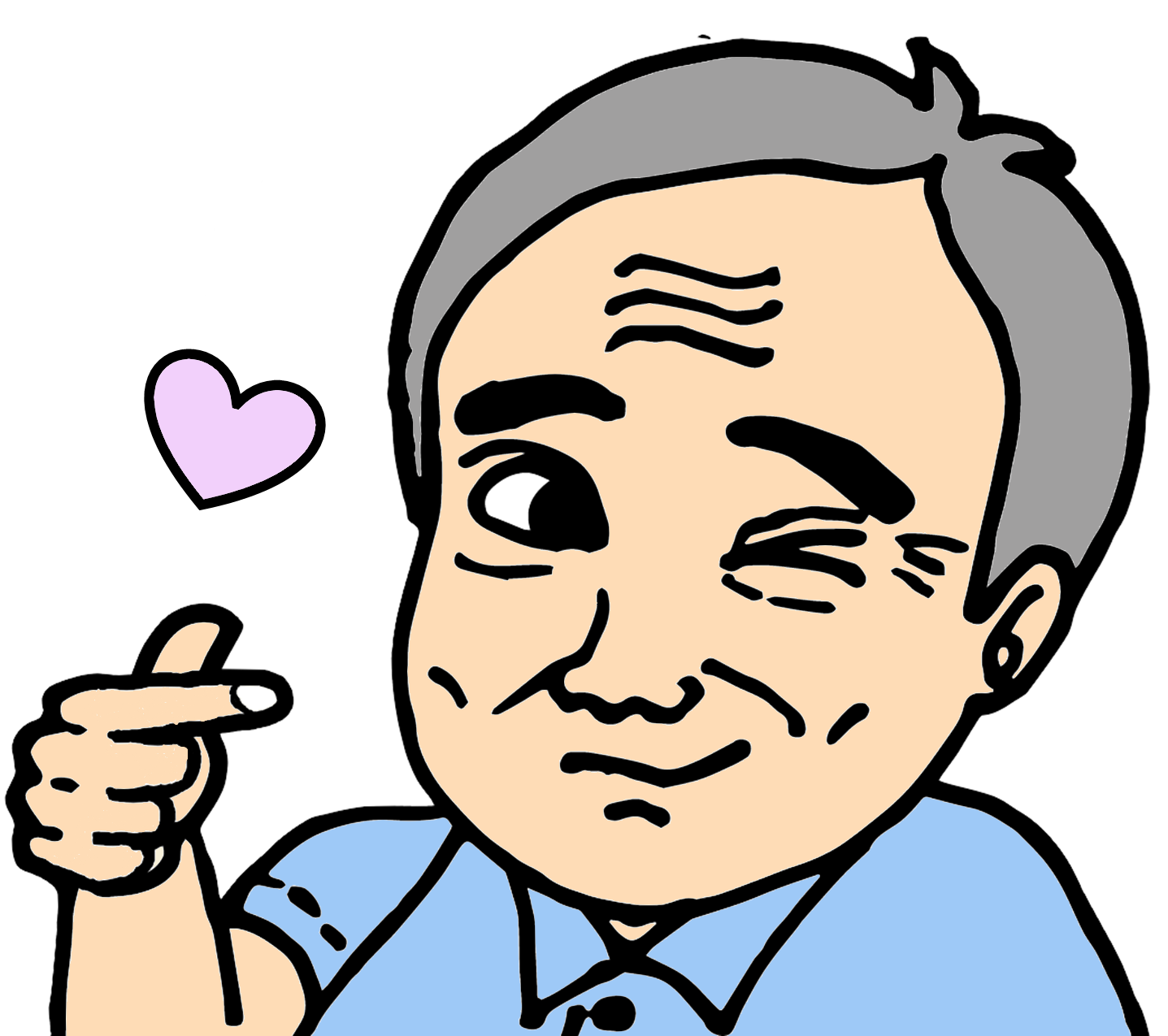踊り場の美学
人のたゆたうところに存する美学。ためらい、ころあい、塩梅、ゆとり、あそび、ゆらぎ、加減、裁量。
踊り場で逡巡し、足踏みして、あれやこれやと思慮を巡らす。なんと人間的ではないか。それは、自らを正す最後の砦であるやもしれん。
このステージで舞い、次のステージへと駆け上がることのみが道筋だとする現代においては、「逡巡している暇はないぞ」と追いはらわれる部分となるのであろう。
昨日K教諭から走れメロスの一節、「信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っているのだ。」や「ただ、わけのわからぬ大きな力にひきずられて走った。」に見える「大きいもの」「大きな力」について問われた。
うまく答えることはできなかったのでここで述べておこうと思う。
勝つか負けるか、白か黒か。物事を明確にはっきりさせることを善しとする通念においては、馬鹿げたものにみえる世界観とでもいっておこうか。言いかえるならば、はっきりとしないところに浮遊する決めつけることのできないあれこれである。人はよくそれを「愛」とか「信実」という。勝ち負けのつかない、白黒のつけられない、割り切ることのできない別の次元にある諸々である。人の営みのほとんどは、勝ち負け・白黒とは無縁のそこに存しており、芸術をはじめとする人間臭さは、この曖昧な踊り場で醸すのである。
逡巡するところに香り立つ美学。これが芸術のエッセンスだ。悩み惑い逡巡するからこそ美しいのだ。ドラマが生まれるのだ。現実世界とはかけ離れたところみえるこれらは、我々の営みのほとんどといってもおかしくはないだろう。教育もこの次元の中にあるべきであった。受験という勝ち負けのつくものに左右され、数値化された結果が学校や塾の評価とされる。間違いなく学校は評価規準とされるものに覆いつくされてしまった。決められたものを決められた方針でゆるぎなく生徒に行使することを強要する。
踊り場こそが、人間世界の人としての営みの存する場。なぜに、踊り場のない社会構造へと邁進する現代。一息つく場所もなく続く階段。転がり落ちたら奈落の底。
「踊り場で足を止めて、時計の音気にしている(思い出がいっぱい〔H2O〕)」踊り場(舞台)で逡巡する姿が人間世界のドラマである。「ああは言ってしまったものの、こう言えばよかった」とか「あのとき気づけばこうはならないのに」と大小に関わらず思いを巡らす。それが踊り場。人の人である場所なのだろう。それでも現代社会はエスカレーターのごとき自動で上る階段ばかりに注視してしまう。そちらの方が重要なのか?
「走れメロス」はシラーの詩である「人質」が基となっている。芥川龍之介が「今昔物語」をはじめとする古典から題材をとったように、想像だが、太宰はこの味気ない硬い話を自分ならこう演出するとして、人間味のあるドラマに仕立てたのであろう。まるで、活動弁士のごとく、臨場感を大切にした話し様。硬く冷たいシラーの詩に温かい人の血を流したのは、太宰だったのかもしれない。もちろん、人のうごめく踊り場で‥‥。