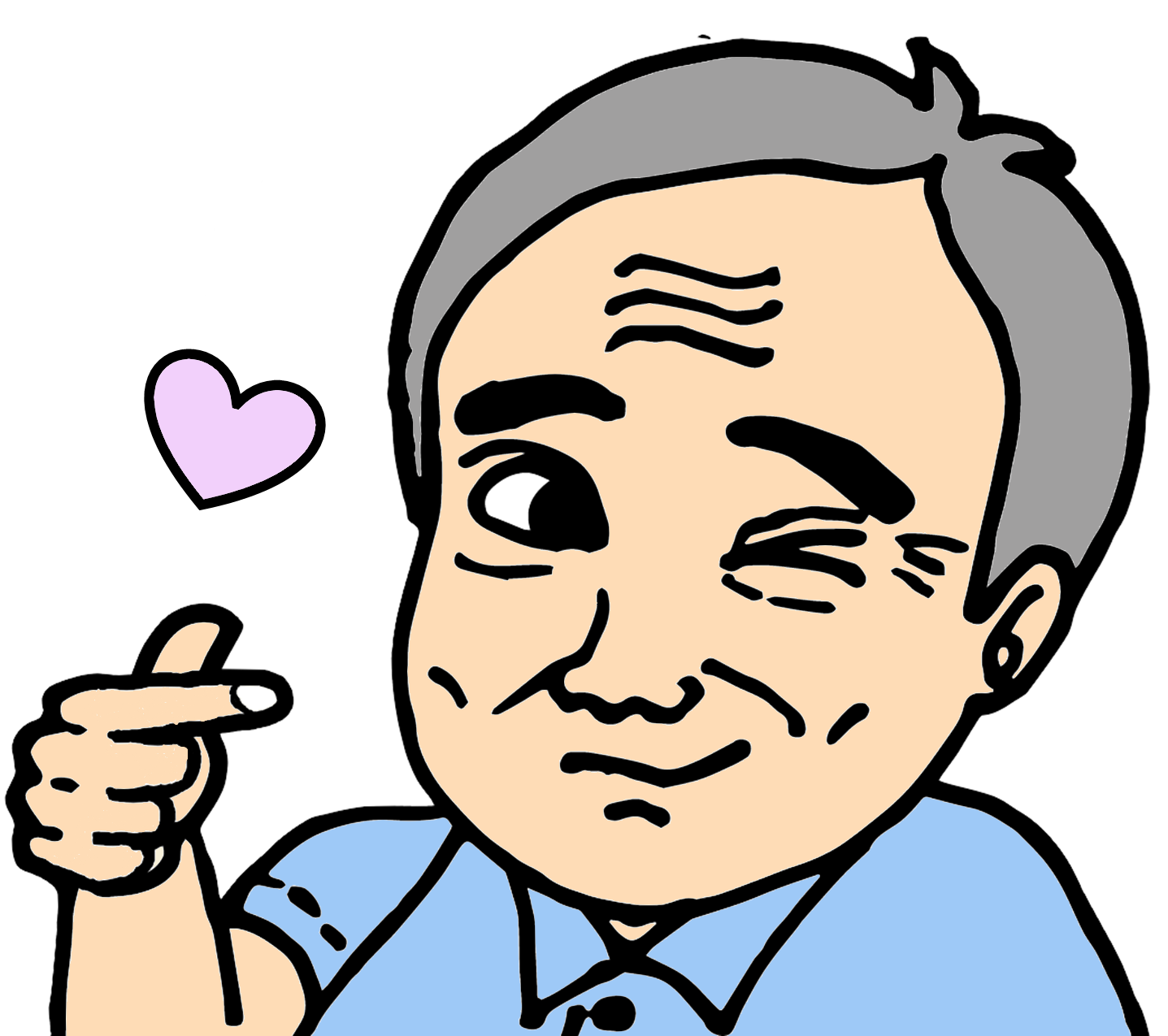オツベルは機械化された農場のオーナーである。多くの農民を働かせ、その頂点に立つ親方的存在である。ナレーター役の牛飼いが「オツベルときたらたいしたもんだ」言うように、ある種のカリスマ性を持った人物もあり、儲けることになによりの価値を感じている。知恵を働かせ、いかに小さな投資で大きな利益を得るか、それが彼の関心事なのだろう。
ところで、そんなオツベルは悪人なのだろうか?ほめられたものではないが、そんな人間は現代にもたくさんいる。つまり、その世が、その時代が、生み出したひとつの人間の姿であり、オツベル自身も悪いことという意識などはさらさらない。あたりまえのごとく自らの価値観にしたがって働いているだけである。
オツベルの最期は援軍の象につぶされてぺちゃんことなる。童話である以上、リアルな描写は当然避けたのだろうが、なんともあっけないのである。勘ぐれば、それほど中身の無いうすっぺらなことに頓着しているのが人間なのだと言っているのかもしれない。
一方白象は、オツベルのところで働き、徐々に体力を奪われて、やがて動けなくなる。白象は森の象の仲間に手紙を書く。「ぼくはずいぶんめにあっている。みんなで出て来て助けてくれ。」これを読んだ森の象達は「オツベルをやっつけよう」という議長の象が高く叫ぶのに呼応して一斉にオツベルのもとへ向かう。やがて、白象は仲間たちに助けられ、”「ああ、ありがとう。ほんとにぼくは助かったよ。」白象はさびしくわらってそう云った。”となる。白象の「さびしいわらい」に垣間見える状況が重要である。助けられたのはうれしいが………。このさびしさの内容を吟味していくと「もっと(オツベルのもとで)働きたかった」という声が聞こえてきてならない。たしかに「助けてくれ。」とは手紙を書いたが、「オツベルをやっつけてくれ」とは書いていない。「オツベルをやっつけよう」と解釈したのは仲間の象達である。自らの思いが違う形で曲解され、目の当たりにされてしまう。そんなさびしさと見て取れるのである。オツベルも仲間の象もみんな悪いやつではないのだが、どこかで屈曲し何らかの行動という形をとって返してくる。相手の思いを何らかの枠組みにあてはめて「こうなら、こうだ」と型にはめ込み、理解しようとするのは、現代でも同じである。
働くことが好きで、純粋無垢で、疑うことを知らず、曲解することのない素直な目を持ち、周りから「お人よし」とか「でくのぼう」と言われようとも、(借り物やマニュアルといった型ではなく)たとえ枠から外れていようとも、自らの内からにじみ出てきた思いをよりどころとして生きよう。自分⇒人間⇒自然⇒地球⇒宇宙。価値観をどこに置くべきか、宮沢賢治に問われている。 END