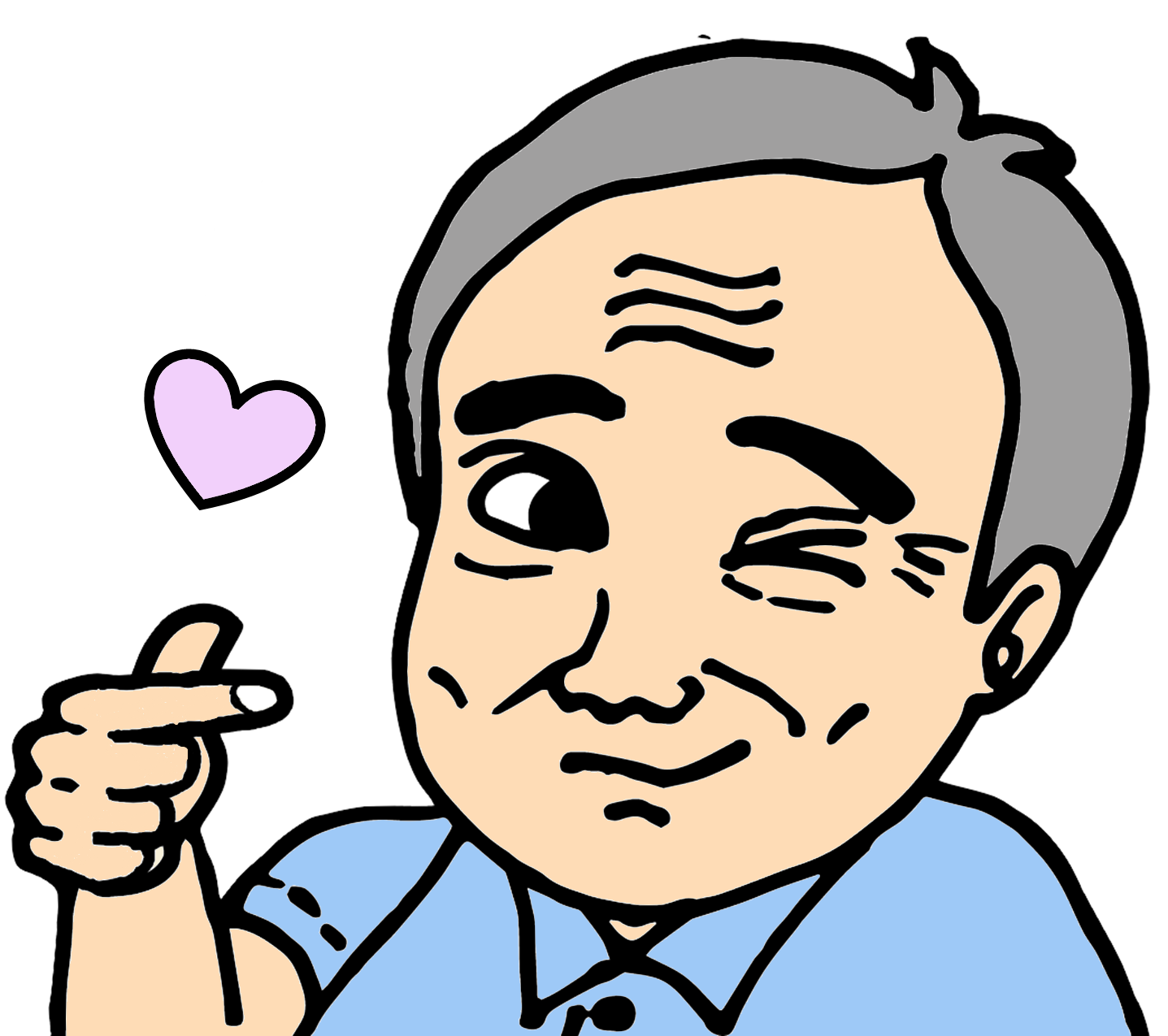ーテクノロジーとの格闘(そして妥協へ)ー
安全・安心を担保するために進化するテクノロジー。自動プレーキ・自動運行、免震・耐震技術など身の安全を守るため産み出されてきた。新幹線の安全神話をかわきりに高度成長期の量産を背面から支えたこれらの技術は、われわれの生活の中に着実に不可逆的に定着していった。昨今のITにしても同じであろう。
空に向けたテクノロジーで言うならば、熱気球、飛行船、グライダー、飛行機、ジェット、ロケット、人工衛星、月探査・衛星探査などの宇宙開発。
さらに飛行機で例えるなら、1903年、エンジンを搭載したダブルサーフェス翼の複葉機であるライトフライヤー号。これが世界最初に飛行に成功した機で、近代飛行機の礎となったことは言うまでも無いであろう。しかし、その5年後1908年には世界最初の飛行大会がフランスで開催されたり、1909年には単葉機ブレリオIXがドーバー海峡の初横断先着競争を征すなど、そのテクノロジー進化の凄まじさは、目を見張るものがあった。そして、それらの新たなテクノロジーに別の新たなテクノロジーを組み込み戦うるテクノロジーと昇華していった。第一次世界大戦(1914.7.28~1918.11.11)では、飛行船への兵器の搭載(恐れられたレッドツェッペリン)、戦争中に急速に増加した軍用機(空爆)、および潜水艦の登場によって、戦争そのものへの概念が変わっていった。それは、「テクノロジーを制する者が世界を征する」というものである。
現在を見るかぎりにおいても、この呪縛というべきものは確実に鎮座している。ロケットに搭載された「核」(ICBM・SLBM)である。大気圏を越えるロケットの技術に原子力技術(核)を搭載し、そのテクノロジーによって、世界を征するという思考である。
こういった国際社会の志向に歯止めを科すために、国際法があるのだろう。前に述べた飛行機については、「1906年に万国国際法学会は、各国の自衛に供されぬかぎり航空は自由という原則を採った。[wikipediaより]」とある。しかし、理想と現実はえてして反目する結果を生み出してきた。アインシュタインが憎きナチスに先を越されてはならぬとルーズベルト宛へ返信した「原子力とその軍事利用」への署名。のちに大国が秘密裏に「核爆弾開発(マンハッタン計画)」を進行し、公表されぬまま行われたトリニティ実験(1945.7.16 アメリカ合衆国ニューメキシコ州ソコロの南東48kmにあるトリニティ実験場で行なわれた人類最初の核実験)の末、3週間後には広島に投下。この広島型原爆(リトルボーイ)はトリニティ実験の際のインプロ―ジョン型ではなく、実験実績のないガンバレル型のため実験込みの初の原爆投下といえる。その3日後にはインプロ―ジョン型長崎原爆(ファットマン)投下。
何はともあれ、原子力の開発が兵器として用いるために行われた事実には変わりがない。原子力発電など、兵器ではない利用目的を見るには、1953.12.8 アイゼンハワーが国連総会で行った原子力平和利用に関する提案(平和のための原子力)を待たねばならない。
テクノロジーが戦争を目的として組み上げられた例ではあるが、この呪縛は現在社会に常に暗い影を落としている。原爆を持つものが、そのテクノロジーを維持するために、平和利用の道を画策し、それを盾として、核存続にむけてははぐらかし、依然として残るであろう最終兵器としての恐怖によっては、核の傘下へ追い込む図式を産み出している。
アインシュタインは日本に投下されたことをさぞかし悔やんだことだろう。ヒトラーを落とすためには武力もやむなしとしてした署名が、陸続きの大陸ではない、東のはずれにあり、周囲が海に囲まれた被害拡大に及ぶ影響が限られた日本という島国に、大いなる損害を与えてしまうことにつながるとは。原子爆弾の実施実験としては最適であったこの国の不運さをも感じえたことだろう。
テクノロジーがその用途をあらかじめ兵器として用いられる約束であったかの核のような例は少ないだろうが、いつのまにかその方向へシフトしてしまうケースは数々あったろう。ライト兄弟が飛行機を兵器として組み上げようとしたとも思えぬし、過去の発明家の多くも戦争利用をもくろんで創り上げたテクノロジーは多くはなかったはずだ。
職人と言われる技術者が血と汗と思いを込めて世に送り出した様々な産物。職人の意図する思いの一部のみを切り出して量産化するに至った社会。教育とて同じであろう。教師という生徒を前にする職人が、自らの感性によって創造することができなくなった。全てが妥協の中で遂行されゆく・・・・。道徳の教科化は道徳の権威をあげるためであって、感性の育みを阻害している。働き方改革は働き方を強要(強制)する方向で動き始めている。