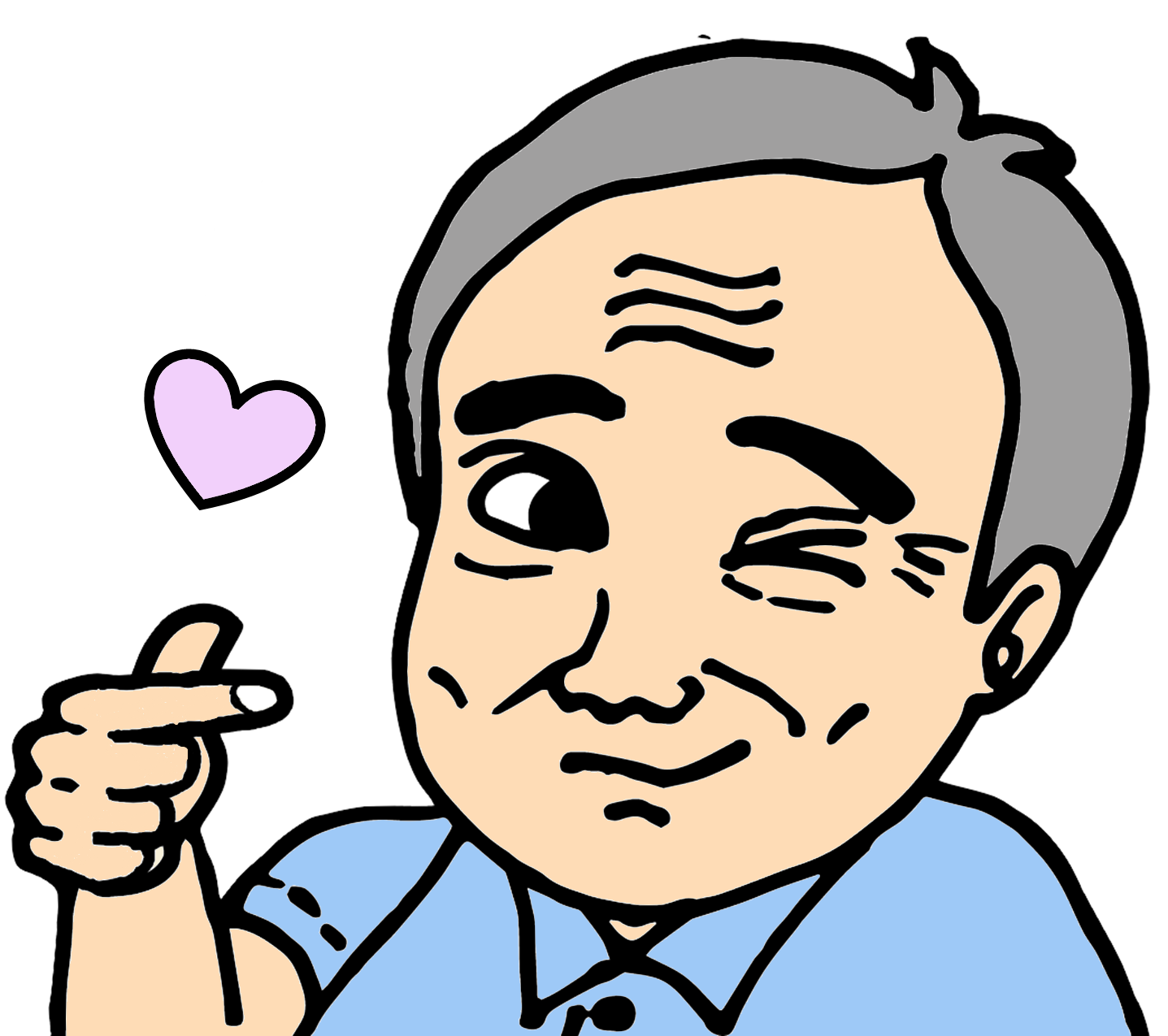皿 西脇順三郎
黄色い董が咲く頃の昔、
海豚は天にも海にも頭をもたげ、
尖つた船に花が飾られ
ディオニソスは夢みつゝ航海する
模様のある皿の中で顔を洗つて
宝石商人と一緒に地中海を渡つた
その少年の名は忘れられた。
麓(うららか)な忘却の朝。
高校生時代にこの詩と出会った。国語の教科書に載っていたそれは、まさにわたしの概念を覆すものだった。先生がこの詩について何か書けと言ったが、何も思いつかない自分がいたのを知ったからだ。ある女子生徒の感想文が読み上げられた。「海を渡るキラキラと輝く船、はじける色‥‥」そんな内容だった。読み上げて先生は絶賛した。「え、それでいいの?」と思いながらも、それを超える衝撃が心に走ったのだ。固定観念や理屈に支配されていた自分を思い知らされたのである。感性というものからものを見つめる目を開かせてくれたのである。
教師になるきっかけを与えてくれたそれは、現在、授業で教材を扱う際にも、これまで言われてきた説にとらわれず、多方面から感覚の潤いを通して見つめる「感覚と同一化できない理屈は嘘だ」という姿勢のもと、教育に向き合わせてくれた。
しかるにこの「皿」という詩自体について、振り返ることがなかったのである。思えばこの詩に出会った高校の時、吹奏楽部に所属していた私は、顧問の先生がコーラス部を兼任していたこともあり、コーラス部にかり出されることもあり、交流があった。「葡萄の歌」という合唱曲があった。自分が歌うことはなかったが、不思議にもメロディも歌詞も覚えているほど印象に残ったところがあった。それは「♪ 葡萄はさすらいの デュオニュソスの手で 世界に運ばれた ♪」の部分である。高校時代に、この交錯する「ディオニソス」から何かを導けたかもしれなかったが、それはなかった。ただただ、感覚のきらめきに魅了する世界を見つめていただけだった。接点らしきものがありながら取り過ごしてきたのであろう。
62歳となった今、あらためてこの詩をみると、シュールレアリスムがどうだかという理屈はもちろん、感じるままでいいという感性だけではない何かが見えてきた。
「黄色い董が咲く頃の昔」とは、かつて菫が、すみれ色(青紫)の補色(反対色)である黄色であったほどの遠い遠い昔ということ→すなわち神話の世界。
そこでは葡萄(ワイン)の神ディオニソスがイルカが舞う海原を航海している。その情景が貼りつく。
ズームアウトしていくその図柄の円形の皿(椀)。その皿には水がはられている。図柄が乱れる。
さらにズームアウト。その水で顔を洗う○○という名の少年を乗せた船(海賊船?)。彼は宝石商人(海賊)と地中海を航海している。
そんな不思議な夢を見ていた自分。大海原を航海する船の中で今目が覚めた。夢の中にいた少年の名は思い出せない。または、史実にも残っていない。何とも麗かな朝。
そんな時空を結ぶ細い糸が見えてきた。神話の世界の大昔)→大航海時代の昔)→現在
さらに、これには続きがある気がする。
現在の航海をズームアウトしていくと地球という皿が見えてくる。地球の航海をズームアウトしていけば、太陽系という皿がある。さらにその先に銀河の皿が‥‥。
人が皿の中で、歴史や生き様というざわめきを演じている。そして、その様子を見ている未来がある。そしてさらに‥‥。というように。
言い換えれば、
自分の前に画面がある。画面の奥に見えるのは画面。その画面には画面が映し出され、そこにまた画面がある。ふと今、自分が振り向いてみると、そこには自分を映し出すだろう未来の画面(カメラ)がある。というものだ。
そんな繋がりというか、繋がりの中に見える拡がりを感じたのだ。何が正解かなんて問題ではない。さらなる深みを、人生の深みを感じ得た今(現在)を思った次第である。
2020.12.17