①この詩の種類(形式)は何か。
口語定型詩と考えるのが一般的でしょう。
しかし、どの形式とも限定できない工夫がなされている詩と考えた方がいいと思います。
◇韻律が感じられる(作者も何らかのリズムを感じつつ描いている)点から見ると、定型詩。
一連 8・5/7・5/7・5
二連 8・5/7・5/7・5
三連 8・5/7・5/8・5
四連 8・5/7・5/6・6
・全体として7・5のリズム(七五調)であり、声に出して読んでいけば、自ずと七五調で読んでしまうでしょう。
ただし、戸惑うところがあるとすれば、四連3行目の「あたりまえだ、ということが。」でしょう。これも、句またがりからなる破調として捉えれば、全体的には七五調の定型詩。
◇細かい改行がなされた今様(現代風)のところから見て、上記破調の部分を重く捉えるならば、自由詩。
◇改行はされているが、句読点が用いられている点、体言止めとなるところがない点などから、散文詩とも考えられる。(改行がなければ、散文となる)
このようなことからはっきりとこの詩の形式を述べさせることは少ないかと思われます。
しかしこれが、金子みすゞさんのねらいであると思えるのです。このことについてはあとで振り返ります。
②この詩の言わんとしたこと(テーマ)は何か。
一通り詩を読んでいくとわかると思うのですが、四連の部分が韻律的にも内容的にも前の連とは違うと感じ取れるでしょう。内容を要約すると、「前の連で述べたような自分がふしぎと思うことを、誰もがあたりまえだと思っていて、ふしぎにも感じないことが『ふしぎ』。」となります。ここに金子みすゞさんの思いが集約されています。
調べればわかると思いますが、恵まれない生涯を遂げた金子みすゞさん。童謡詩人として、詩人西條八十さんから称賛され、脚光を浴びますが、後に詩作を夫から禁じられ、やがて離婚、生まれた娘の親権のもつれから自ら命を絶ってしまいます。忘れ去られる運命を宿していたかに見えた金子みすゞさんの作品を復活させたのが矢崎節夫さんです。金子みすゞさんの弟と奇跡的に巡り会うことができ、遺作も発掘できたのです。
大正から昭和に代わる時代。これまでには、樋口一葉や与謝野晶子など有名な女流文学者はおりましたが、それでもこの時代の文芸において、女性であることの厳しさが強かったことは想像できるでしょう。「女は家を守れ!」とか「女が働くなんぞとんでもない」とか、とても制約の多かったことだろうと思います。世間が「あたりまえ」としていることのなかに潜む矛盾や偏見、確証・実感のない理解(思い込み)に対する反発を感じてなりません。世間が「物事を決めつけてしまうことによって『あたりまえ』のことだして理解し、すり替えていく」姿勢に強い疑問を抱いたのでしょう。子供があげるような純粋な疑問を、子供だからといって頭ごなしに排斥しないでほしいのです。
令和の現在においても、金子みすゞさんの言葉は、生きていると思えませんか。昭和初期と同じ構図がこの令和の初期にもあると思えませんか。だからこそ、金子みすゞさんの詩は輝きを失うことなく生き続けていると言えます。
詩の形式に話をもどすと、金子みすゞさんは、内容面で誰もが思いもつかない新感覚の詩の表現を模索したのは間違いないと思われます。世間は彼女の詩に何か真新しさを感じてはいても、「ああ口語の定型詩だね」とくくって、決めつけてしまうことに金子みすゞさんは反発したのではないかと思います。
③表現技法について
「ふしぎ」の詩で用いられている修辞法としては、a倒置法 b反復法 c押韻(頭韻・脚韻)があげられます。
解説によっては、「対句」をあげるものもあります。一連の「黒い雲からふる雨が、/銀にひかっていることが。」と二連の「青いくわの葉たべている、/かいこが白くなることが。」を対句ととらえる考え方です。色の対比はなされていますが、同じ構成で並べられているかと言えば、厳密には対句というのには無理があります。
しかし、作者金子みすゞさんが全く対句を意識していなかったかというと、そうでもありません。
対句という技法は中国から伝わってきたもので、中国の詩(漢詩)の決まりごととして用いられるものです。4行(四句)で書かれる漢詩を「絶句」というのですが、杜甫の「絶句」という詩は一行目(起句)と二行目(承句)が対句になっています。「絶句」という形式は、起句と承句は必ずしも対句にしなければならないという制約はないのですが、しばしば、起句と承句が対句で表現される場合があるのです。金子みすゞさんの「ふしぎ」で言うと、一連が漢詩で言うところの起句にあたり、二連が漢詩で言うところの承句にあたります。対句であるとは言えないまでも、対句を意識していたとは言えるでしょう。
◇まとめ
彼女の詩の作風は、真新しいものばかりにベクトルが向いていたとはいえないのです。新しき方向性を向くときもあれば、古(いにしえ)を向くときもあるのです。つまりとても自由なのです。自分から生まれ出た感覚と合致するなら、古いも新しいもないのでしょう。それぐらい自分の感覚(感性)を自分の思いを大切にしている詩人と言えるのです。この古いも新しいもないことが、すなわち、令和の現代においても彼女の詩が輝いている理由でもあるのでしょう。そして、未来に向けても。
謎を謎と感じる心
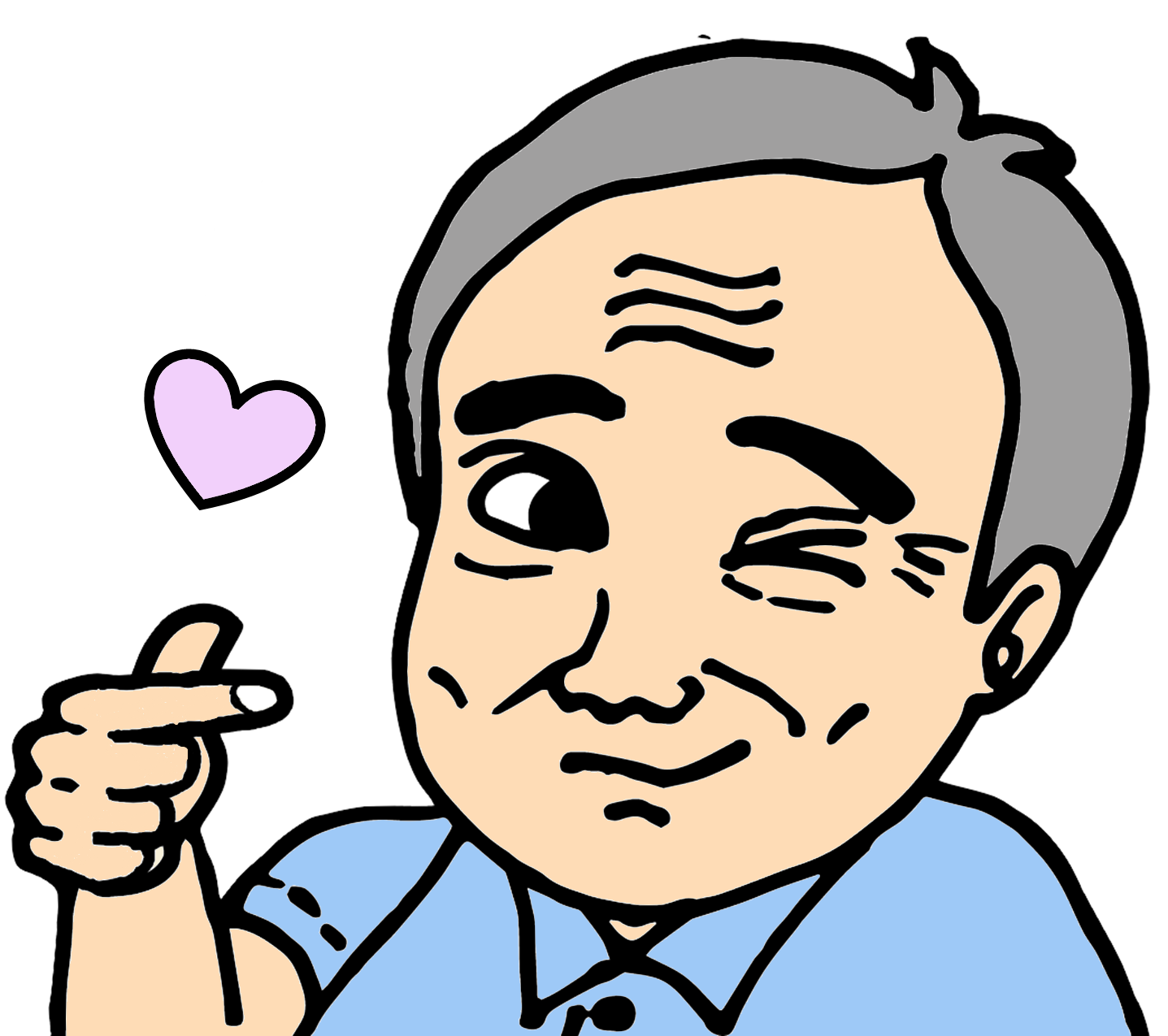
ほのぼの研究室

-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
メタ情報
