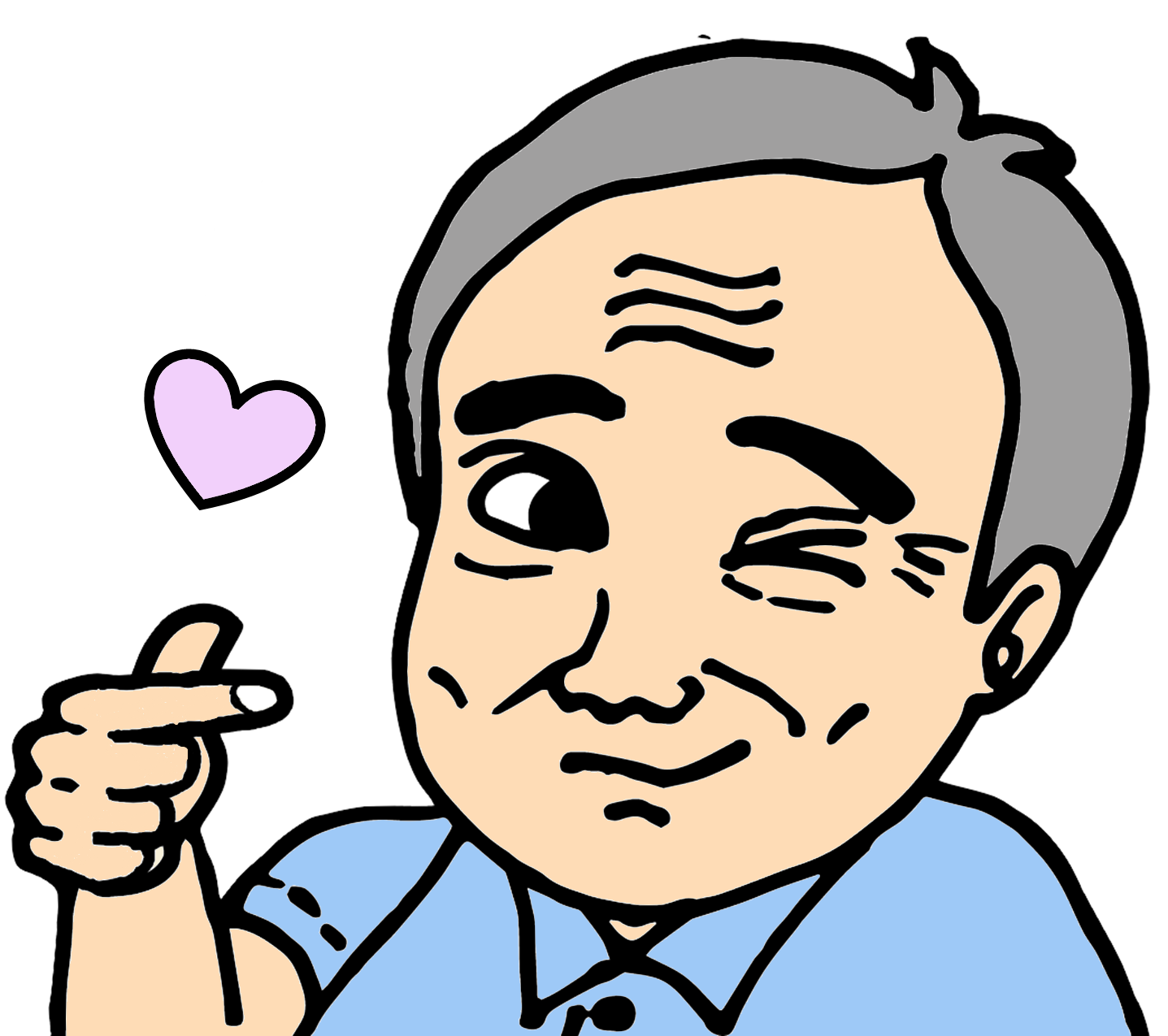もともと仏教の教義の一つであった無常。仏教伝来とともに日本に渡ってきたのは容易く理解できるが、現代に至るまでわが国の情操の中枢にある価値観として活き続けているのはある意味驚きでもあろう。万物流転の法則ともいえるこの無常観。常では無い。「世にあるものはそのままであり続けられるわけではなく、移りかわっていくものである。」という教義。我々日本の多くの人の心の奥底に今でも宿しているかと思う。
「無常」という言葉にはもとからはかなさを伴うところは確かにあったろう。唐代の詩人杜甫が「春望」の中で「国破れて山河在り 城春にして草木深し(長安の都は戦に敗れ落ち、山と河が残った。城内は春を迎え、草木が生い茂っている。)」と詠んだ。解釈によって印象は多少変わる部分はある。「草木深し」を荒廃した城内を助長するすさんだ姿ととるか、荒廃した城内ではあるが青々と生命の息吹を感ずる草木が生い茂った姿ととるかである。ただどちらでとるにしても変らないのは、長安の城内が変ったことなのである。長安の都とて、かわりゆく宿命を負うということにかわりはないのだ。そう見ていったとき、仏教の無常観は日本伝来のもととなる中国でも、唱えられていたのは当然のことだろう。
ただ、日本では、「無常」というものを必要以上に陰(イン)の方向へシフトしてしまったと感じている。そうなった背景として、仏の教えが全く届かぬ「末法(末法思想)」が影を落としたことや同音の「無情(情けなし)」と結びついてしまったことが考えられる。それゆえもの悲しさを纏ったはかなくもせつない陰の意味合いが強まった気がする。平家物語をはじめ徒然草など無常観を著す文献は山ほどある。そのほとんどが、あとに残る余韻の情景(余情)が暗くせつないのだ。藤原定家にいたっては「空想の絵画歌人」とか「歌の枯山水」と言いたいくらいストイックにつき詰めた殺風景な陰の情景を余韻に残す。芭蕉とて無常を尊ぶ歌人(俳諧師)の一人ではあるが、彼の場合はこれまでの詩人歌人とは一味違うと思う。その違いとは、残る余情がプラス指向、つまり陽の情景を余韻に残すようにしているところなのである。
「おくのほそ道」の冒頭の段に挿入された発句「草の戸も住み替はる代ぞ雛の家」。残る味わい(余韻として残るの)は、雛人形をかざる子供のいる温かくもきらびやかな家族の情景であり、それが残像として浮き彫りにされよう。対比の関係にある芭蕉が住んでいるころの庵は「江上の破屋」であり「草の戸」であり、自分が旅に出て長く家を空けていると蜘蛛が古巣を張ってしまうようなひなびた庵である。そのもの悲しさという負の陰の残像を余韻として残そうと芭蕉はしていない。芭蕉は生まれ変わった新たな庵の旅立ちを祈念しているのである。すべてのものが旅人であるなら、庵とて旅人であってしかるべきだ。庵を旅立たせよう(庵に新たな庵の人生をおくらせよう)としたのである。残る味わい(余韻)に、前向きで、力強くもあり、明るくもあり、華やかでもあるプラス指向のイメージを描くことを意識していたといえるのではないか。
また平泉に到着した芭蕉は、五百年前の奥州藤原氏の繁栄の名残りを「大門の跡は一里こなたにあり」とか「金鶏山のみ形を残す」と述べている。高館(義経堂)に至っては高館は残っておらず、雑草ばかりが生い茂る変わり果てた様子に直面し、杜甫の詩をはさむ。負の様相を拝した無常を唱える句をここで芭蕉は残すかと思いきや、義経主従と泰衡の軍がここで戦う姿を二重写しにした状況を描く。その句が「夏草や兵どもが夢の跡」である。実際に目の前にあるのは荒れ果てた雑草の生い茂る高館跡ではあるが、余韻として残るのは、双方がそれぞれの夢を描いてたくましく戦い、切り結ぶ情景であろう。ここでも芭蕉は、陰に落とさず、陽にむけた味わいとして残すよう努めているようにみえる。さらに、この平泉では「五月雨の降り残してや光堂」の句も残す。鞘堂で金色堂(光堂)を覆ったお陰で朽ちることなく残っていたのだ。芭蕉にとってこの感動は句に残すにあたいする。大門の跡はあくまで跡であって南大門が残っていたわけでもなく、人工の山金鶏山とて五百年の間にその雄姿はかなり薄れていただろう。高館にいたっては、跡形もなく雑草に覆いつくされていた。これまでのあるにはあるがの遺跡とは違い、この光堂は、当時を偲ぶことのできる実景として目の当たりにすることができたのである。このように芭蕉は己の心が動いた(感動した)時に句を残すと私は思っている。
長い年月の中で「無常」というものが、徐々に陰の様相を深めていった。陽の様相として移り行く無常を描いたのが芭蕉であったと思う。そしてその陽の様相を残す試みは、のちの蕉風の中の「軽み」につながる芭蕉の理念とも言えよう。
たしかにそれ以前にも芭蕉の敬慕する西行が「道の辺に清水流るる柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ」と芦野の地で余韻に陽の味わいを残したものがある。
西行の足跡をたどる旅ともいわれるおくのほそ道の旅。西行の場合は鎌倉が奥州に睨みをきかせる構図の中で平泉を目指した。芭蕉の場合は江戸が日光東照宮修復手伝いを負わすこととなる仙台藩に睨みをきかせる構図の中で平泉を目指す。中央が奥州を睨む似た構図の中、当時の西行師匠がどんな思いで平泉を目指したのかを同化する形で知りえたかったのだろう。西行師匠はおそらく奥州藤原氏の行く末と義経の行く末を案じていたのだろうと思いながら。
無常が画一化した陰の理念となって行く中で、芭蕉は無常のもつ多様性を拓いていったのだと思う。
無常とて移り行くかな初鴉