報道規制が強まるロシア国内の状勢。ジャーナリズムは、真実とは言えずとも、ありのままを発信することも許されない。それどころか、嘘をかぶせて報道する状態にさえある。ロシア国内の人々の声はほとんど聞こえてこない。挙句国営放送のキャスターらが反乱から辞職する様態。かつての日本がそうであったように、もどることが叶わぬ返しのついた一本道を皆でひたすら突き進むような状態にある。戦争はやめるべきと思うロシア国内の一般人も確実にいるだろうが、それを発したり、意見したり、議論したりする場が統制され皆無となっているのである。
バイデン大統領は言う。「ウクライナの状勢は民主主義と専制主義の戦いである」と。プーチンという独裁者が思いのままに内外に猛威をふるう様子から見ると、プーチンは専制主義者であることはわかるが、それが民主主義との戦いであるとするには、アメリカおよび西側諸国、そして日本も、専制性のまったくない民主主義を実践していなければならないはずだ。だからバイデン氏の言葉はある意味正しいのではあるが、言葉による意識の扇動がはらんでいる気がしてならない。
戦いたくもない相手と戦わなくてはならない戦場という現場にいる兵士や庶民‥‥。彼らの思いや情況が政局に反映されることはない。とにかく現場は実行するのみ。
現場というリアルな空間の声を聞く民主主義は、専制国家だろうが民主主義を名乗る国家だろうが存在しないのかもしれない。現場は上の決めたことを自分の判断を交えず粛々と行うことに終始する。
戦時下の話だけとは言えないからこそ、見極める目を持つべきだろう。
問題を抱えた現場の声を聞かず、現場にはいない当たらず触らずの無責任な大多数の声に権力者の恣意を混ぜて、これを民主主義と称えるのだ。民主主義を名乗る国であろうとも専制国家のそれと同じ様相を醸し出すのである。
教育の現場も大きく変わってしまった。一教師がその学校の運営に携わることはなく、会議の席にもつけない状態なのだ。そもそも職員会議なるものも、「民主主義」同様、聞こえのよい言葉として使われているだけで、実質「会議」の様相は呈していないのだ。だから、困窮する学校現場の声は黙殺されていく。企業も同じだろう。民主国家を名乗る国の社会全体のシステムが専制化してしまい、皆で善き方向へと模索し創り上げる側面は消えていった‥‥。
「白髪レガシー」を書き始めた肝はここにある。教育こそは嘘で塗り固められた世論に同化することなく泥臭く地に足をつけて育む姿勢を失ってはならない。実感を伴う学びを子供たちに与えていかなくてはならない。人々が民主主義という実感を得られぬまま、これが民主主義であるとすり込まれぬよう注視しなくてはならない。
2022.3.27
謎を謎と感じる心
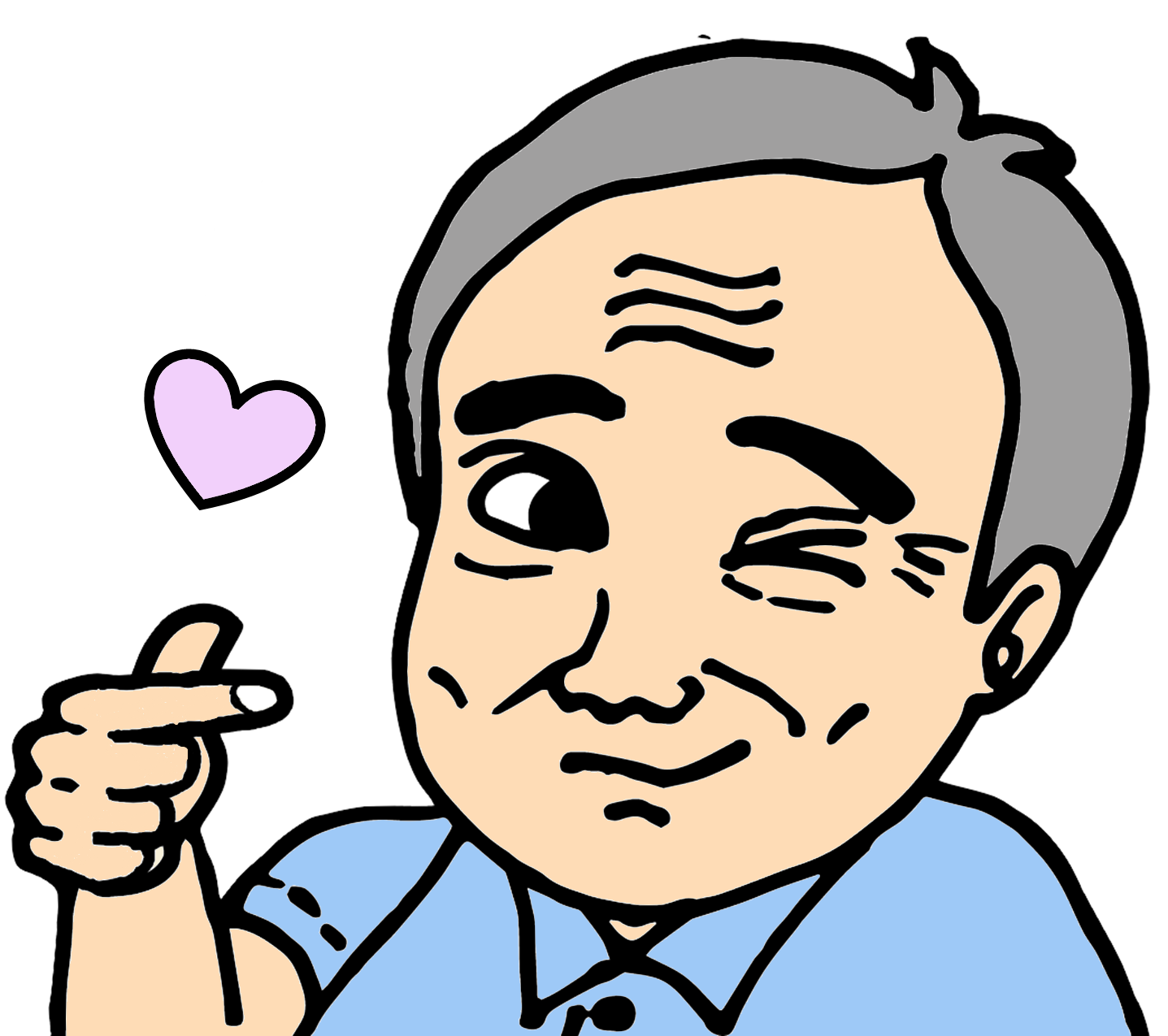
ほのぼの研究室

-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
メタ情報
