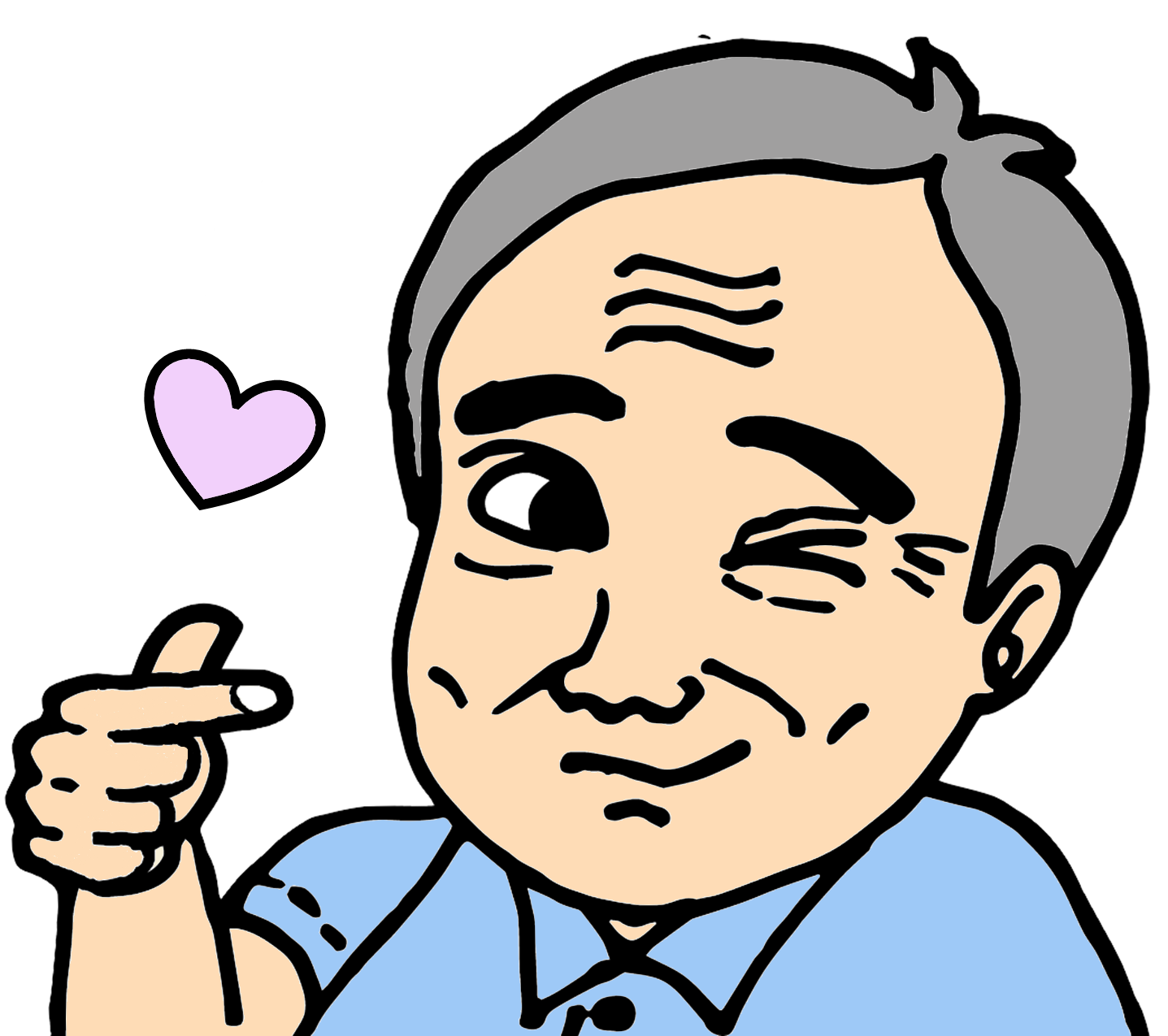芭蕉忍者説について
2025/03/29 放送のテレビ朝日「博士ちゃん」でもふれられていた「芭蕉は忍者だった」について、私の見解を述べてみます。
「芭蕉の出身は伊賀である。老齢にしては健脚である。関所(関門)を安易に通ることができた。忍者の教科書には隠密の化する適職は俳人とある。仙台では句会を開かずこそこそしていた。」あたりが、その根拠として述べられていました。
ロマンをこめて、あえて反論したいと思います。
芭蕉が隠密だとして、まずわからないのが「何のため?」ということです。幕府の密命を携えて、旅の俳人に化け、当時の仙台藩が負わされた東照宮修繕に絡み、謀反を企てているかどうかを探るためということでしょうか。また、「おくのほそ道」の旅だけは特別の隠密行だったというのでしょうか。
状況証拠(客観的根拠)としては、成り立つかもしれませんが、目的という内面的な情状(情緒)をくみ取った根拠とは、いえない気がしてしまうのです。
私としては、「敬慕する西行師匠の心境に迫ろう(同化しよう)」とみちのくの旅に赴いたと考えています。その根拠としては、元武士西行(上皇の身辺を警衛する北面の武士であった)の出家後の謎めいた(隠密めいた)行動に見て取とれます。奈良東大寺焼失の勧進(寺院の修繕のために、浄財の寄付を求めること)を名目として、奥州へ赴いたことです。
西行が奥州向かう当時1186年といえば、前年に義経・行家追討の院宣(後白河法皇が一度は義経の説得のもと「頼朝追討の院宣」として出したが、後に頼朝の怒りをうけ、機嫌を払拭するために出したもの)が出されており、平家討伐の立役者であった義経が兄頼朝に追われている状況なのです。西行は、奥州行きを打診するため、鎌倉に寄り、頼朝と面会します。西行の名目(表向きの理由)は先にも述べた勧進なのですが、どうもそれだけではない気がするのです。時勢を鑑みれば、「もしかしたら義経は、世話になった平泉に逃げ入るかもしれん。」と頼朝も含め、誰もが考え得るところでしょう。その最中で西行は奥州へ向かうのですから。
頼朝からすれば、平家討伐を終え、今後の気がかりといえば、これまで沈黙を貫いてきた奥州藤原氏なのでしょう。頼朝は、西行が奥州藤原氏と同じ藤原秀郷の子孫であることも承知していたでしょうし、たとえ西行が敵となるかもしれぬにせよ、義経が平泉に入ったり、西行がよからぬ画策を講じたならば、奥州藤原氏撲滅の大義(理由付け)がたつのですから。
中央(鎌倉)が、奥州(藤原氏)に睨みをきかせる構図の中で、行脚するのが西行なのです。この謎めいた(隠密めいた)行動の意図は藤原秀衡に頼朝の思惑や動向を伝えんとしたのかもしれません。
これと同じような構図となるのが、芭蕉の奥州行きの時です。
中央(江戸)が、奥州(仙台藩)に睨みをきかせる中で、芭蕉は平泉に向かうのです。この芭蕉の謎めいた状況が、隠密論を生み出しているように思えるのです。500年という歳月の隔たりの中に見えたふしぎな符号点。ただし、芭蕉は密命を携えて旅した隠密ではなく、師匠西行が500年前のあの時に、どんな思いで平泉へ旅をしたのだろうかと気になっていたのだと思います。きっと、似たような構図の状況下で行脚すれば、師匠の思いを垣間見、体感(同化)することができると考えたからではないでしょうか。
芭蕉が幕府のスパイ(隠密)とはどうしても思うことはできません。どちらかというなら西行同様、弱者である仙台藩を気づかっていると思える次第です。
違う時代に似たような構図の中で行脚する「時の旅人」。それが、芭蕉を謎めかせてみせる理由だと思っています。西行かぶれの芭蕉は師匠の思いの丈に触れたかったのでしょう。
芭蕉は、古人の一人「宗祇」が崩れかけた俳諧連歌を格調高いものへと戻し確立したのと同様に、俳諧がおちゃらけて滑稽なものがあたりまえとなっていく中で、格調もあり、芸術性の高い、それでいて前向きな温かみのあるものを創設せんとした芸術家であると信じたいです。決して策士ではないと‥‥。
2025/03/30
芭蕉の美的価値観 芸術性について
おくのほそ道は虚構が多いなどと言われるが、それは、芭蕉自身の美観に正直であったところから来る部分も多かったためと思われます。
例としてあげておきましょう。
閑さや岩にしみ入る蟬の声 <立石寺>
有名な句なので知っている人も多いでしょう。わたしが、この句の最も素敵な点といえば、「しみ入る」という言葉を生み出したところです。
この句は次のような推敲のすえこうなりました。
山寺や石にしみつく蝉の声
↓
さびしさや岩にしみ込む蟬のこゑ
↓
閑さや岩にしみ入る蟬の声
なんだ何回も書き直してんじゃん!うそっぽくね!と思う人もいるでしょう。ただ、ここでもう一度、どの形態が一番いいと感じるか、振り返ってほしいと思います。
おそらく、なんだかんだ言っても、やはり最終形態が一番いいというところに落ち着くでしょう。特に「しみ入る」という言葉をあみだした点です。芭蕉は山寺(立石寺)を訪れた時の情感を「しみつく」ではどこか違うという気がしたのでしょう。また、「しみ込む」でもないとも感じていたのでしょう。やっとの思いで絞り出されたのが、芭蕉自身の感覚とマッチした「しみ入る」だったと考えられます。
「しみ入る」には、「しみつく」や「しみ込む」に感じられる押しつけがましさ(強引さ)がない点です。「しみ入る」は、自然とそうなるといった自発的な感覚が組み込まれた言葉だと感じられるのです。〔文法的にではありません〕
岩にしみ入り、芭蕉の心にしみいった山寺の景観。掛詞の要素を踏んで感じてあげるとよいでしょう。蝉の声はおそらくかなり大きな音量で響いていたでしょう。しかし、その声は、芭蕉にとって決して苦々しいものではなく、心地よい響きだったのでしょう。それゆえ、うるさいはずの蝉の声を「閑かさや」という対比関係にある快い情景にしあげたと考えられます。これは、芭蕉がそのとき感じた正直な感覚なのだと思います。
暑苦しくうっとうしくもある蝉の声が、自然に閑静で涼しげな心地よい情感として芭蕉の心にしみたのだと思います。二考目の「さびしさや」にある「さびしい」というネガティブな感覚も、「閑かさ」と入れ替え、ポジティブな心地よさ。前向きな情緒として描こうとしているようにみえませんか。
芭蕉は、自分が感銘した光景を、どう表現したら、正しく伝えられるかを追求した芸術家だと思います。自分の感じた感動をなにより発句には正直に描こうとしたのだと思っています。
松島で句を残さなかった件について
芭蕉が松島で句を残さなかったのも、芭蕉自身の心に正直な感動が芽生えなかったからかなと、わたしはみています。自分のポリシー(信念)にそぐわぬことを残そうとは思わなかったのでしょう。たしかに松島の風景はそれなりにすばらしいものではあったでしょうが、冒頭で思い描いたような「松島の月まづ心にかかりて」ではなかったでしょうし、また、それを超えるほどの新たな感動が実際の松島で味わえなかったのではないでしょうか。
—芭蕉が思い描いた松島の光景は、島々と満月のコラボで、それはそれはどれほど素晴らしいかと心を躍らせたものでした。しかし、実際の「おくのほそ道」の旅で松島に訪れたのは、旧暦5月9日で、満月ではなく九夜月(九日目の月)であり、月がはっきり見えるころには南中高くにあったと思われます。松島の雄島で海面に映る月を地の文(文章部)で述べていますが、海面に映る月ということは、月が高い位置にあったことであり、方位として見ても、島々に懸かる月ではなかったのです。満月でもなく、島々にかかる月でもなかったことが芭蕉の期待を超えなかったところでしょう。それでも、期待以上の別の新たなすばらしい光景が芭蕉の心に芽生えたならば、必ずや句は残したと思われます。
当初この松島で「島々や千々に砕きて夏の海」と詠みましたが、この句は不満だったとみえて、残されませんでした。ここからも芭蕉は自身の美観に正直にありたかったからだとうかがえます。
芭蕉の句には余韻として残る味わいに、プラス志向の前向きな良さを残すよう努めていると思われます。
2025/04/04 2025/04/11 追記